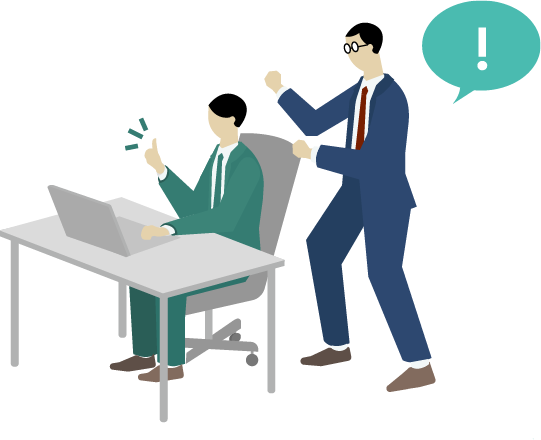実際の業務をハンズオンで経験しながら学べるOJTは、新人育成の場面において効果的に活用できる手法です。しかしながら、OJTを取り入れているのに、なぜか新人社員に充分な教育効果が現れていないという悩みが生まれる場合もあるでしょう。
OJTは教育する側の適性にも気を配る必要があり、指導者として適性のない人がOJT教育担当になると、新人社員のモチベーションの低下や教育期間が長くなるなどの問題があります。
この記事では、OJTの指導者として向いていない人や向いている人それぞれの特徴、そしてOJTとOFFJTの違いについて解説します。
OJT指導者に向いていない人の5つの特徴
OJTは知識が豊富で仕事ができる社員が担当するのが良いと思われがちですが、そうではありません。残念ながら仕事が出来てもOJT指導者に不向きな人は存在します。
ではOJTの指導者として向いていない人の特徴にはどのようなものがあるでしょうか。以下には、その代表的な特徴を5つピックアップします。
1. 否定的な言葉を使い間違いを正す教え方をする人
まず挙げられる特徴は「否定的な言葉を使う人」です。
新人教育の場面では、新人社員にスキルや知識をつけさせることも重要ですが、その仕事を続けていけるようにサポートすることも重要です。
このような場面において否定から入るスタイルで話を始める指導者や、人の否定ばかりするようなタイプの人が指導者をしていると、新人社員の心が先に折れてしまい、OJTの場面で貴重な将来の戦力を失いかねません。
どんな話し方が否定的か、下に2つの例を出してみました。
| よくする間違いを指摘する場合 | |
|---|---|
| NG | 「いつもここを間違えているよ」「ちゃんと確認した?」 |
| OK | 「ここは難しいところだから、次からこうすると間違えにくいよ」 |
| 新人社員の出した答えへのフィードバック | |
|---|---|
| NG | 「いや、これは現実的とは言えないね。」「ちゃんと勉強してきた?」 |
| OK | 「目の付け所は良いね!次は今できることで考えてみよう。」「ここは間違えやすいから、もう一度おさらいしておくと良いよ」 |
こんな事まで気を付けなくてはいけないのかと思うかもしれませんが、提案や承認する言葉を選ぶことで、否定的な言葉を使わなくても間違いを指摘はできるのです。
OJTの場面においては間違えても責めたり叱ったりする必要はなく、間違いは間違いとして訂正や指導するようなスタイルが求められます。
そのため、OJTの指導者は感情をコントロールし、成長を促すようにサポートできる人が適しています。決して人格を否定するような言葉を投げかけてはいけません。
2. 自分の仕事しか見えていない人
OJTとは、指導者のもとで通常業務から知識を身につけていく教育方法です。
そのため、教育担当者の業務量によっては丁寧に仕事を教える余裕がなく、かつ未経験エンジニアに任せられる仕事もなく、新人社員をほったらかして自分の仕事に追われてしまうことも多いのです。
会社にとって人材育成は非常に優先度の高い業務です。OJT指導者は、会社の財産である人材の教育を任されるわけですから、社内全体であらかじめ業務量を調整しておくなどの工夫が必要です。
よって、自分の仕事第一な人に加えて引き継ぎが難しい仕事を多く担当している場合がOJT指導者も担うのは難しいかもしれません。
融通が利く業務を担当していて、自分の仕事だけでなく社内全体の状況把握ができる人が向いていると言えるでしょう。
3. 仕事は見て覚えるものだと思っている人
かつての仕事現場では、仕事は「教えてもらうもの」ではなく、「見て覚えるもの」「見て盗むもの」という考えを良しとする風潮がありました。確かに身体や手先を使うような特定の技能職においては一部そのような面がありますが、しっかりと指導者が教えながら業務を行ったほうが成長が早くなるケースが圧倒的に多いといえます。
特に、エンジニアは「見て学ぶ」という学び方に適しておらず、実際に頭を使い手を動かすことで知識が定着し成長していく仕事内容です。
「見て覚えろ」「見て盗め」という価値観でOJTをしている指導者のもとでは、結果的に新人社員の育成期間が長くなりOJTが逆効果になってしまう可能性が高いのです。
4. 後輩に対して愛情、敬意がない人
OJTにおいては指導者と新人社員とが近い距離感でともに業務を行い、長く同じ場所で過ごすようになります。結果的にそこから信頼関係が生まれ、成長が促されるというのがOJTの理想的な形です。
しかし愛情や敬意がないと、それが言葉や行動にあらわれてしまいます。愛情のなさを感じた新人社員は萎縮してしまったり業務へのモチベーションを失ってしまったり、双方にストレスばかりが蓄積する結果となりかねません。
指導者が外向的である必要はありませんが、相手への敬意が足りないと感じる振る舞いをする人や、そのつもりがなくても誤解されやすい人はOJTの指導者としては避けた方が良いかもしれません。
5. OJTの目的を理解できていない人
OJTの指導者というのは、実は自ら指導者を買ってでるというケースはあまりなく、どちらかといえば上司からの命令や役職上の流れでOJTの指導者となっているケースが多い傾向にあります。
それ自体はある種やむを得ない部分もありますが、いつまでも「やらされている」という状態は、OJTの効果を得られない無駄な時間となってしまうケースが多いといわざるを得ません。
OJTを通じて新人社員に何を伝えていくのか、どのようなスキルを身につけてほしいのかを明確に認識し、言われたとおりに指導するのではなく積極的に会社の一員を育てる姿勢が求められます。
「言われたことはやる」という受動的なタイプよりも、能動的に動ける人が向いています。
OJT指導者に向いている人の特徴

ここまではOJTの指導者に向いていない人の特徴を解説してきました。
以下には逆にOJTの指導者に向いている人、適正がある人の特徴をピックアップします。
褒め方・注意の仕方が上手い人
OJTという教育課程において「褒める」という行為は非常に重要です。人は褒められることで無意識にモチベーションがアップし、よりよい結果を出すためにさらなる努力をしようとする傾向があります。
しかし、いつも「いいね」だけでフィードバックを終えてしまうといったような褒め方では良い効果に結びつきません。
「この前より早く終わっているし、このチェックの方法もとても良いね!自分で考えたの?」
など、結果的に修正があったとしても、スピードやミスの量、成果物からは見えない工夫についても具体的に褒めると、しっかりと見守られている安心感から仕事へのモチベーションも上がります。
一方で、注意するスキルも重要です。新人社員が誤った方法をとっていたり、業務に向き合えていないと感じたりしたときにただ感情的に叱るのではなく、再びモチベーションを取り戻し誤りを改めていこうと思えるような注意の仕方ができる人もまた、OJTの指導者として適正のある人といえます。
分かりやすい説明ができる人
OJTにおいては、新人社員に様々な「説明」をしなければならないケースがあります。説明がわかりやすいことは、成長を早める結果に結びつきます。
わかりやすい説明には「結論を先に話す」「あいまいな言い方をしない」などの「話し方のスキル」も影響する部分があります。
また、新人社員がわからないことについて、一緒に調べてあげることや、疑問を持つポイントについてしっかりと知識をつけるなどの努力ができる人も、OJTの指導者として適しているでしょう。
OJTのデメリット
OJTには教育すべき内容をハンズオンで教えられること、教育の中で信頼関係を構築できることなどのメリットがあります。
一方で、新人教育の中でOJTを取り入れる際には、以下のデメリットについても把握しておきましょう。
社内全体の業務効率が低下する
業務内で教育するため、当然のように指導者の業務ペースは遅くなります。
あらかじめ指導者の業務量を調整していても、その業務は社内の別の社員が対応するため、結果的に社内全体のリソースがやや不足する事を考えなくてはなりません。
今までは社員達のスキルによって滞りなく進んでいたプロジェクトも、スケジュールに余裕をもたせておく必要があるでしょう。
指導者によって効果に差が出てしまう
OJTは指導者と新人社員との間での業務を通じたハンズオン教育となります。実態に即した知識が得られるというメリットの反面、書籍や講座などのような体系的で網羅的な知識を得るためには、指導者の側に深い見識と経験の両方が必要です。
そのため、指導者によって効果や期間に差が出てしまう可能性があります。
これは結果が出なかったり、期間が延長になった新人社員にとって、その後のモチベーション低下にもつながったりするため、慎重に対策をしなくてはなりません。
複数の指導者が必要な場合は、同じようなプロジェクト経験がある者から適任者を選出するなどして可能な限り差が出ないように努める必要があるでしょう。
OJTとOFFJTの違い
OJTが「On The Job Training」の略であり、実践を通して仕事を教わるという形式であるのに対して、OFFJTは「Off The Job Training」の略です。
このOFFJTは、実際の仕事の場ではなく、座学や集合研修などを通じて人材を育成する手段です。
OFFJTは短期集中で業務知識を身につける場合や、仕事の土台となる予備知識を習得させる目的に合致する方法であり、OJTとOFFJTはそれぞれの目的によって実施されます。
今はOJTを重視する企業が多いですが、OFFJTはOJTでは抜けてしまった知識を補填することもできるので、同時に導入するとインプットとアウトプットの環境ができるため新人教育には効果的です。
OJTだけではなくOFFJTも取り入れたい場合は「StoneStackr」を導入しよう

先に解説したように、OFFJTには座学や研修によって、業務の前提となる知識をしっかり身につけさせるという目的があります。このような場合には「StoneStackr」がおすすめです。
StoneStackrは、未経験エンジニアを自走できるエンジニアへ育成するためのeラーニングサービスであり、「実際の案件に基づくコーディング課題」や「学習計画機能・仕様書機能」「管理者ツールによる学習管理」など、新人社員・教育者の双方にとって大きなメリットのある育成サービスです。
「StoneStackr」で学んだことは、OJTでアウトプットに繋げればより身につきやすくなるでしょう。
自社エンジニアの育成においてOJTやOFFJTを取り入れようと考えている際は、ぜひStoneStackrの導入も検討してみてください。