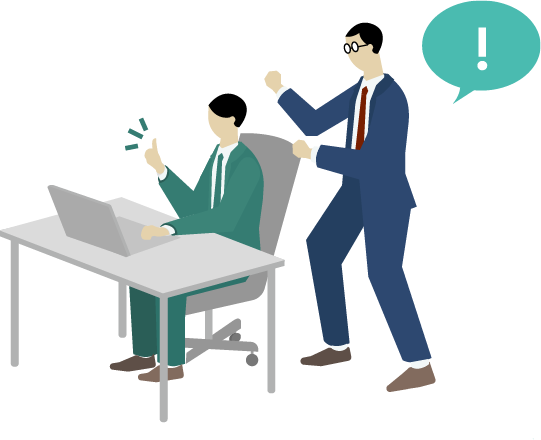新入社員の育成は将来的な企業成長に大きく関わります。「できるだけ早く現場で活躍できる人材を育てたい」とは考えていても、実際にどのような新人研修カリキュラムを組めばよいか分からないという担当者もいるのではないでしょうか。
この記事では、新入社員の早期成長を促すために、新人研修カリキュラムに組み込むべき内容や効果的な手法を具体的な事例を交えて解説します。
新人研修カリキュラムを作成する目的とは?
新人研修で社会人の基礎を学び、エンジニアとして活躍してもらうためにはカリキュラムを作成する必要がありますが、根本的な目的や内容を明確化することが大切です。内容を具体化するために活用される手法として、5W1H形式があります。
5W1H形式と明確にするべき内容は以下の通りです。
・Why(根拠)
新入社員のスキルアップ、現場レベルへの早期育成
・What(目的)
一般的なビジネススキル、業務知識(専門知識)、マインドなど
・Who(対象)
新入社員(全体/特定の業種)
・When(日時)
〇月〇日(または期間)
・Where(場所)
〇〇会場、オンライン会議など
・How(手法)
OJT、グループワーク、eラーニングなど具体的な手法
研修の日程や場所、実施方法だけでなく、「なぜこの研修が必要なのか」や「この研修を通じて何を達成するのか」といった根拠や目的を明らかにすることで、研修の目標とビジョンが明確になります。
新人研修カリキュラムに盛り込むべき2つの内容
研修の詳細を明らかにしたら、具体的に研修カリキュラムを作成していきます。5W1Hの「1H」を考慮して、盛り込むべき内容を落とし込んでいきましょう。
ソフトスキル
ソフトスキルには、基礎的なビジネスマナーやチームワーク、対人関係の構築、問題解決能力などがあります。エンジニアの新人研修において重要なのは、ソフトスキルの中でも「ロジカルシンキング」と「コミュニケーション」の習得です。
ロジカルシンキングは、日本語で「論理的思考法」と言われるもので、ロジカルシンキングの能力を鍛えることで、問題解決に対して道筋を立てて取り組めるようになります。エンジニアは、エラーやバグなどの不具合が発生したときに、原因を特定し解決策を導き出すスキルが求められるため、この能力の習得が必要です。
コミュニケーションは、他人に対して自分の意見を明確に伝え、相手の意見を正確に理解する能力です。この能力は特にチームでの作業を円滑にし、生産性の向上に役立ちます。対話だけでなく、メールやチャットを多用する職場では文章力も求められるでしょう。
ハードスキル
新卒社員の場合、特定の職種で採用されても、そのほとんどが職種未経験者です。研修ではビジネスマナーを習得すると同時に、早く実際の現場で活躍できる専門スキルを身につける必要があります。
エンジニアなどの専門職の場合、プログラミングスキルや特定の専門知識の習得が重要です。また、モバイルアプリ、Webアプリ、ゲームアプリなど、大規模開発案件をパターン別に実践を伴うトレーニングも必要となります。

新人研修カリキュラムは何をする?3つの教育手法を解説
新人研修でより良い効果を得るためには、効率的に学べるカリキュラムを考えることも大切です。新人研修では様々な方法がありますが、ここでは主な手法3つを解説していきます。企業に合わせて適切な方法を選びましょう。
eラーニング
eラーニングは録画コンテンツをパソコンなどで視聴しながら学んだり実践したりできる学習方法です。株式会社 Innovation & Co.の調べによると、eラーニングシステムを導入している企業は55.1%となっており、半数以上の企業がeラーニングを使用しています。
その理由として、学習すべき内容を録画・デジタル化することで時間や場所を選ばずにいつでも学習できるというメリットがあります。
特に通常業務が忙しく研修に多くの時間をかけられないという企業でも、日時を調整する必要がなくスキマ時間を使って学習してもらえるほか、繰り返し視聴できるため個々の能力に合わせて理解力を深めることが可能です。
ポテンシャル採用でも、いつでも学習できる機会を持つことで教育コストの費用対効果が高くなる可能性もあります。
出典:株式会社 Innovation & Co.
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03901/fe28c55b/6908/49f7/9ae7/fc8453e248e1/140120221214578307.pdf
OJT
OJT(On-the-Job Training)は、先輩や上司と行動を共にし、実際の業務を見たり実践したりしながらスキルを身につける方法です。単なる「学習」や「体験」に留まらず、実践的で効果が高い手法といえます。
指導する立場では、実地での状況に合わせて指導も行い、必要に応じて改善を促していく必要がありますが、指導役の主観で偏った考えや技術になる可能性も懸念されます。「ハンズオン(※)・ラーニング」を意識しながら、実践教育を計画していきましょう。
エンジニアの場合は、一般的に実践の前に業務フローや仕組みを説明し、実際に計画書の作成や開発に携わりながら進捗状況や成果物をその都度チェックします。案件によっても工数やプロセス、ルールなども変わるため、予め計画を説明することが大切です。
※ハンズオン:IT分野に置けるハンズオンは、エンジニア向けの勉強会や講習会に取り入れられる「実践的な学習」を指し、講師が実際に操作方法を教えながら受講者自身も実際に手を動かして学ぶ形態です。
出典1:MoneyForward『ハンズオンとは?意味は?支援の仕方・形式を解説!』https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/64219/
グループワーク
グループワークは、個々で実践するのとは異なり、複数人で協力しながら学習できるというメリットがあり、対人関係を深めたりコミュニケーションスキルを向上させたり、ソフトスキルを磨く機会にもつながるのがメリットです。
一般的には、講義を受けた後に一定の時間が設けられ、話し合いながらプログラムなどを作成し、その成果を発表または提出します。エンジニアにとっては、チームで開発することが多いため実際の業務での考え方や行動などにも役立ちます。
グループワークには「作業形式」「プレゼン形式」「ゲーム形式」などがあり、目的に合わせて選ぶことが重要です。
| 作業形式 | 与えられた目標を達成することを命題として、所属グループのメンバーと協力して作業を行う形式 |
| プレゼン形式 | 与えられたお題に対してチーム内でアイディアを出し、チームの意見として改良した上で発表する形式 |
| ゲーム形式 | コンセンサスゲームやブロックゲーム等のように、与えられたお題に対して各グループ協力して答えを出す、文字通りゲーム形式のワーク |
【3Step】新人研修カリキュラムの作り方
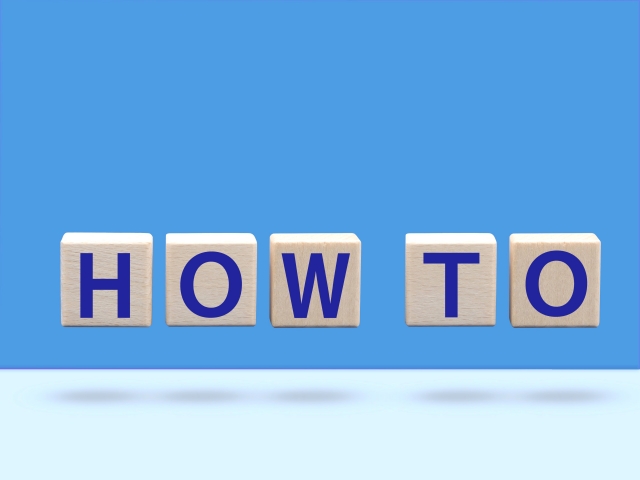
カリキュラムの目的や手法を理解したところで、実際にカリキュラムを作っていきます。研修カリキュラムの構築は、複雑なプロセスのように感じられますが、基本的な3つのステップに分け、内容を段階的に整理しましょう。
Step1.新人研修の目標を設定する
カリキュラムに限らず、物事を進めるためには目標を設定することが重要です。ビジネスにおける目標設定には、「SMARTの法則」や「WOOPの法則」などが利用されます。SMARTの法則は5つの目標達成に必要な基準の頭文字をとった目標設定方法で、WOOPの法則は、目標設定から達成までを4つのステップに分けたもので、あらかじめ起こりうるネガティブな事象を考え、その対処法までも計画しておく手法です。
SMARTの法則
| 具体的な/Specific | 目標は具体的にする(○○の資格試験に合格する) |
| 測定可能な/Measurable | 目標は達成まで測定できるのか(合格点数) |
| 実現できるのか/Achievable | 現実的な目標なのか(自分がチャレンジできる級) |
| 関連した/Relevant | 自分の利益に関連しているのか(資格取得手当がもらえる) |
| 期限が明確な/Time-bound | 具体的な期限はあるか(来年の○月にある試験を受ける) |
WOOPの法則
| 願望/Wish | 何がしたいか(資格を取得したい) |
| 結果/Outcome | 叶ったら自分はどうなるのか(資格取得手当がもらえる、仕事に対して自信がつく) |
| 障害/Obstacle | 起こりうる障害はなにか(帰宅後は疲れて家で勉強ができないかもしれない) |
| 計画/Plan | 起こりうる障害の解決方法を計画する(朝の通勤時間を勉強時間に充てる、できなかった日の分は土日に勉強する) |
どちらも目標達成に向けた考え方や実践方法を指標にしたフレームワークで、1つずつ書き出して資料にしてまとめると分かりやすく、行動しやすくなります。
たとえば「入社して〇日から〇日まで△△の研修を行う」「この期間までにプログラミングの演習を完了する」などカリキュラムと同時にスケジュールも考えましょう。
Step2.配属部署にヒアリングを行う
具体的な研修内容を決める前に、それぞれの配属部署でのヒアリングを行いましょう。たとえば、営業ではビジネスマナー、総務ではOAスキル、ITエンジニアであればHTMLやJavaの基礎といった専門スキルなど、部署によって求められるスキルやレベルが異なります。
部署内でも、管理職と2年目の社員など、異なる立場からの声を聞き、必要なスキル、望ましいスキルなどについて理解を深めましょう。部署の要望を反映することは、最終的に戦力として活躍できる人材育成につながります。
Step3.研修方法を決める
ヒアリングを元に必要なスキルを特定し、研修方法を決めていきます。前述したeラーニング、OJT、グループワークなどを表にしてそれぞれの特徴や負担、費用、メリット・デメリットなどを比較しましょう。
企業のリソースには限りがあり、教育には時間がかかるため費用対効果を考えながら自社に合わせて最適な方法を選びます。
前年に行った内容を見直し、改善していくことも大切です。特に世代が変わると、考え方や持っているスキルも異なるため適切かどうかを判断し、より生産的な研修カリキュラムを構築しましょう。
新人研修カリキュラムの企業事例2選
研修カリキュラムを考える際に、他社の成功事例を参考にするのもおすすめです。ここでは、多くのエンジニアを抱える2社の新人研修カリキュラムを紹介します。
ソニーグローバルソリューションズ株式会社
ソニーグローバルソリューションズ株式会社では約3か月間の研修期間を設け、ITに関する基礎的な知識を学んでいきます。知識の習得と合わせてシステムについて実践的な研修を行い、エンジニアとして知識のない人、経験のない人でもキャリアを積める仕組みを作っています。
その後は各事業の窓口や運用・保守業務など指導役と一緒に実際の業務に携わりながら、半年間の「育成期間」を設けて学習していく仕組みです。
また3~5年を目安に、クラウドやRPA、データサイエンスなど特定の領域のスキルアップ、またはスキルチェンジにも対応しています。
株式会社日立システムズエンジニアリングサービス
同社のITエンジニア育成は、個人のITレベルに応じて基礎知識講座、情報処理技術者試験対策講座、Javaプログラミング基礎、Windows操作などを行い、初心者でも学びやすい環境を整えています。
専門教育期間はSEコースと営業・コーポレートコースに分かれ、SEコースではHTML、TypeScript、SQL、データベース、システム開発総合演習などを行い、プログラミングの習得から開発設計、プロセス体験などでモノづくりを意識した実践力を身につけていきます。その中でレベル分けを行い挫折しにくい、継続して働ける仕組みを作っています。
新人研修カリキュラムで迷ったら「StoneStackr」を導入しよう

StoneStackr
人材育成には長期的な目線で計画を立てる必要がありますが、目標や期間、手法などを精査することで適切な研修カリキュラムを作成することが可能です。
ただし、通常業務も行うため担当者の負担が大きくなっているのも事実です。現場で通用する人材を育てるためのリソースや時間に悩んでいるならエンジニア育成のためのeラーニング「StoneStackr」がおすすめです。
「自走できるエンジニアになること」を学習の目標としており、学習の設計から実践、課題抽出、進捗管理など一貫したサポートを行っています。